都市空間計画区域
今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:04:33
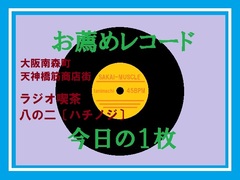 ◆◇◆其の五十五:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
◆◇◆其の五十五:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
●1160年 《武士の時代》
「保元の乱」(ほうげんのらん)で勝利した第77代天皇は後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)は歌手に目覚めて今様(いまよう)が本職の暫定天皇だった為に、1158年に息子の第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)に皇位を譲位(じょうい)して、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)に就く。
その後、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と共に平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)と藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)が政権を主導する。
藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)とは、藤原武智麻呂(ふじわらむちまろ/公家)の南家(なんけ)の系統で、少納言や僧侶を務めた。
藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)の妻は藤原朝子(ふじわらちょうし/公家)で第77代天皇の後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)の乳母を務めている。
藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)は非常に優秀で、藤原氏南家(なんけ)だが鳥羽上皇(とばじょうこう/朝廷)に気に入られて朝廷では高い位に就いた。
ある時、鳥羽上皇(とばじょうこう/朝廷)の一門が、大和国(奈良県)の東大寺は正倉院(しょうそういん)で開催される恒例の“正倉院展”を観覧する為に行幸(ぎょうこう)に出掛けた。
鳥羽上皇…『なんじゃこりゃ? 赤色をした小箱はぁ?』
側近…『う〜〜ん さぁ〜 女官の化粧道具入れですかねぇ〜』
藤原信西…『それは、1983年に任天堂から発売されるファミリーコンピュータです。 略してファミコンと呼びます。』
鳥羽上皇…『ほほぉ〜 ファミコンかぁ! これは世界中で支持される日本の宝であるぞぉ!』
ファミコンの名付け親は藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)である。
この藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)の藤原氏南家(なんけ)と、勝利した後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)の思惑(おもわく)により「平治の乱」(へいじのらん)へと発展していく。
院政(いんせい)が始まる前は、藤原氏北家(ほっけ)が摂関政治で実権を握り、そこに仕えていたのが源氏だった。
一方、天皇家による院政(いんせい)が始まり朝廷の実権を握ると、白河院(しらかわいん)など上皇(じょうこう)の御所を警備や護衛をしたのが平氏だった。
勝てば官軍の後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)にしてみれば、藤原氏南家(なんけ)の藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)や平氏の平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)を寵愛(ちょうあい)するのが人情である。
特に後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)は、藤原朝子(ふじわらちょうし/公家)を介した乳繋(ちちつな)がりの乳兄弟でもある。
しかも平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が率いる天皇軍平氏隊は、戦(いくさ)に遅れて参戦したのに、大活躍して勝利に導いた総大将の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)よりも恩賞が多く官位も昇格している。
この裏には、平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が、戦勝祝いに後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)と藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)などを招待して、木屋町の女郎サロン“ミルクパイ”で接待していた事が影響している。
これらにより、藤原氏北家(ほっけ)の藤原忠通(ふじわらただみち/朝廷→天皇)や源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は朝廷では冷遇された。
この平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)と藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)の傲慢(ごうまん)さに不満を持ったのが、武功の過小評価で冷遇された源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)と、藤原氏北家(ほっけ)の自尊心(プライド)を傷付けられた藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)で、平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇)と藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)に対して1159年に反乱(クーデター)を起こす。
藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)とは、藤原房前(ふじわらふささき/公家)の北家(ほっけ)の系統で、後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)の寵愛(ちょうあい)を受けて中納言を務めた。
ある時、藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)は、平氏の拠点である鴨川沿いに六条周辺の六波羅(ろくはら)に潜り込ませた間者(かんじゃ/スパイ)から、ある情報を得て源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)に伝達した。
藤原信頼…『平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が少ない手勢で“熊野詣”(くまのもうで)に出掛けたらしいぃでぇ、紀伊国(和歌山県)の南端まで行くから、少なくとも2週間は帰って来(け)えへぇんやろ。』
源義朝…『よっしゃ! 憎っくき藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)を討つには今がチャンスやぁ!』
藤原信頼…『せやぁ、せやぁ、憎っくき藤原氏南家(なんけ)を討つでぇ〜 今こそ藤原氏北家(ほっけ)の力を見せたぁんでぇ〜』
源義朝…『あのぉ〜 すみませんが、その力の抜ける様な関西弁を止めてもらえますか? 兵士の士気が下がりますので。』
藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は源氏軍を結成して、烏丸御池の交差点の南東方に建つ後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)の御所だった東三条殿(ひがしさんじょうどの)に進軍する。
源氏軍はその寝殿造(しんでんづくり)の屋敷に居た皇室の侍従(じじゅう)や女官であろうと、片っ端から首を刎(は)ねた。
後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)は牛車に揺られて内裏(だいり)に逃げ込む。
後白河上皇…『♪心に沁(し)みる〜 皇位の輝き〜 今日は牛車に揺られては〜 溜息(ためいき)をつく〜』
後白河上皇…『♪悲しくて〜 悲しくて〜 とても遣(や)り切れない〜 このやるせ無さ〜 モヤモヤを〜 誰かに告げようか〜』(♪悲しくてやりきれない)
後白河上皇…『いやぁ! ええ曲できたでぇ〜 レコードにしたら売れるでぇ〜』
さすがは歌手に目覚めて今様(いまよう)の経験をしてきた後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)である。
どんな状況に置かれても創作活動は忘れない。
そして、藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の目的は、ただ1つ!
藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)を斬首して晒し首(さらしくび)にする事だった。
ところが、6500㎡(1966坪)はある東三条殿(ひがしさんじょうどの)の何処(どこ)を探しても藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)が見つからない。
そしたら日本庭園に不自然な盛土(もりど)がある。
そこを源氏軍の武士が掘ったら、何と泥塗(どろま)れの藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)が出てきた。
こうして源氏軍に拘束された藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)は、藤原氏北家(ほっけ)の藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の目的通りに藤原氏南家(なんけ)の藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)は斬首されて鴨川の河原で晒し首(さらしくび)となった。
BOBBY DARIN /♪ SPLISH SPLASH
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:05:37
◆◇◆其の五十六:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
源氏軍もここまでで終わっておけば良かったが、藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は、更(さら)に後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)を拘束して大内裏(だいだいり)で監禁してしまう。
後白河上皇…『♪今〜 私の〜 願い事が〜 叶うならば〜 翼が欲しい〜 この背中に〜 鳥の様に〜 白い翼〜 着けてください〜』
後白河上皇…『♪この大空に〜 翼を拡げ〜 飛んで行きたいよ〜 悲しみの無い〜 自由な空へ〜 翼はためかせ〜 行きたい〜』(♪翼をください)
後白河上皇…『いやぁ! ええ曲できたでぇ〜 レコードにしたら売れるでぇ〜』
さすがは歌手に目覚めて今様(いまよう)の経験をしてきた後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)である。
どんな状況に置かれても創作活動は忘れない。
此処(ここ)で紀伊国(和歌山県)の“熊野詣”(くまのもうで)へ参拝しに行っていた平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が戻って来て、早速、平氏の拠点である六条周辺の六波羅(ろくはら)で平氏軍を結成して応戦する。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)は戦略を2段構えで実行する。
先(ま)ずは大内裏(だいだいり)で監禁されている後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)する。
続いて藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)が率いる源氏軍に反撃する。
そこで源氏軍が布陣する陣営に間者(かんじゃ/スパイ)を送り込み、難易で高度な皇族救出作戦を実行する。
その皇族救出作戦とは、源氏軍に監禁され牢獄に入れられている後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)に、間者(かんじゃ/スパイ)が女性用の衣類を渡して、それを着た2人は女性のふりをして外出し大内裏(だいだいり)から脱出する。
これが見事に成功した。
この皇族救出作戦は、日本初の“ミスターレディ”と認定されている。
後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)は、金閣寺と太秦の中間に建つ真言宗(しんごんしゅう)のお寺の仁和寺(にんなじ/御室)に身を寄せて、オムロンの体温計と血圧計で体調に異常が無いかチェックする。
看護婦…『はい、服の袖(そで)をまくって、血圧の健康チェックしますからねぇ〜』
後白河上皇…『看護婦さん、オッパイ大きいねぇ〜』
看護婦…『まあ、イヤらしい! もう、自分でチェックしてくださいっ!』
バタン
看護婦さんは、怒って部屋から出て行ってしまった。
後白河上皇…『♪掴(つか)み掛けた〜 熱い腕を〜 振り解(ほど)いて〜 君(看護婦さん)は出て行く〜 僅(わず)かに震える〜 清い白衣に君の〜 巨乳の悲しみを見た〜』
後白河上皇…『♪医務室に向かう長い廊下で〜 何故(なぜ)だか急に〜 君は立ち止まり〜 振り向きざまに〜 巨乳を見せて〜 悲しそうに笑った〜』
後白河上皇…『♪獣(けもの)の様に俺は〜 襲い掛かる〜 若い力で〜 やがて君は〜 静かに倒れて落ちた〜』
後白河上皇…『♪疲れて〜 眠る様に〜 僅(わず)かばかりの〜 意識のなかで〜 君は〜 何処(どこ)を〜 感じたのか〜』
後白河上皇…『♪ You are Queen of Queens!(王女の中の王女!)』
後白河上皇…『♪立たないよ〜 もうそれで十分だ〜 おお神よ〜 私を〜 救いたまえ〜』(♪チャンピン)
後白河上皇…『いやぁ! ええ曲できたでぇ〜 レコードにしたら売れるでぇ〜』
さすがは歌手に目覚めて今様(いまよう)の経験をしてきた後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)である。
どんな状況に置かれても創作活動は忘れない。
第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)は平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が布陣する六波羅(ろくはら)の屋敷に匿(かくま)われた。
此処(ここ)で平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が率いる平氏軍は、第2段目の作戦に出る。
後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)が脱出した事により、戦況不利と考えて源氏軍では逃げ出す武士も多くいた。
藤原氏北家(ほっけ)の藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)、それに援軍として参戦した清和源氏の系統の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が布陣する大内裏(だいだいり)の守備や防御は見るからに手薄となっている。
そんな隙を突いた平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が六波羅(ろくはら)で指揮する平氏軍は、叔父である平頼盛(たいらよりもり/朝廷→平氏)が率いる平氏軍1号隊と、息子の平重盛(たいらしげもり/平氏)が率いる平氏軍2号隊を出陣させた。
平頼盛(たいらよりもり/朝廷→平氏)とは、平忠盛(たいらただもり/朝廷→平氏)と藤原氏北家(ほっけ)の系統の池禅尼(いけのぜんに/藤原→平氏)の息子である。
先(ま)ず、源氏軍の陣営の大内裏(だいだいり)を東方から平氏軍1号隊と平氏軍2号隊が攻め込み、源氏軍が東方の防御に人勢を集中させている隙に、大内裏(だいだいり)の西方から別働隊の平氏軍3号隊が突入して源氏軍を挟み討ちにした。
この攻撃により源氏軍の多くの兵士は逃亡し、大内裏(だいだいり)に残った兵士も平氏軍により斬殺された。
藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)と源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)らは20人あまりの少ない手勢で逃亡し、そのまま平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)が布陣する六波羅(ろくはら)にゲリラ攻撃を仕掛ける。
これが源氏と平氏の因縁の対決となる「六条河原の源平合戦」の始まりである。
しかし、六波羅(ろくはら)は平氏の本拠地で多くの平氏方の武士が住んでおり、多勢に無勢で源氏軍の敗北は明らかな上に、此処(ここ)で源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が平氏軍に寝返り、源氏軍は致命傷となり敗北する。
源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は逃亡して尾張国(愛知県)に辿(たど)り着く。
藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)は、御室(おむろ)に建つ仁和寺(にんなじ/御室)に居住する後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)を訪問して、恩赦(おんしゃ)を求めて命乞いをするが認められず、六条河原に連行されて斬首された。
後白河上皇…『♪下駄を鳴らして〜 奴(藤原信頼)が来る〜 腰に刀(かたな)〜 ぶら下げて〜 兜(かぶと)と鎧(よろい)に〜 染み込んだ〜 血生(ちなま)臭いが〜 やってくる〜』
後白河上皇…『♪ああ〜 戦(いくさ)よ〜 良き敵陣よ〜 おまえ今頃〜 どの戦地で〜 俺と敵対し〜 あの指物(さしもの/旗)見つめて 何思う〜』(♪我が良き友よ)
後白河上皇…『いやぁ! ええ曲できたでぇ〜 レコードにしたら売れるでぇ〜』
さすがは歌手に目覚めて今様(いまよう)の経験をしてきた後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)である。
どんな状況に置かれても創作活動は忘れない。
この藤原氏北家(ほっけ)の藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)と源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の反乱(クーデター)は失敗するが、平氏軍の藤原信西(ふじわらしんぜい/朝廷→天皇→平氏)は討死し、源氏軍の藤原信頼(ふじわらのぶより/朝廷→天皇→源氏)は斬首、源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は敗走し尾張国(愛知県)の知多半島の野間(のま)まで逃亡するも、ここで味方に裏切られ入浴中に討死する。
これを1160年に起こった「平治の乱」(へいじのらん)と呼ぶ。
戦後処理として平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)は、源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の息子でまだ子供だった源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)を斬首にする予定だったが、継母の池禅尼(いけのぜんに/藤原→平氏)に嘆願(たんがん)され伊豆国(静岡県)への流刑になる。
池禅尼(いけのぜんに/藤原→平氏)とは、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の父親の平忠盛(たいらただもり/朝廷)の正妻で、藤原氏の北家(ほっけ)の系統。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)のこの判断が大きな過ちになるとは、まだ、知る由(よし)もない。
DION /♪ THE WANDERER
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:06:33
◆◇◆其の五十七:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
そして、源氏で忘れてならないのが源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)である。
源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の側室で“京都一番の美女”と言われた常盤御前(ときわごぜん/町人→源氏→平氏→藤原氏)と3人の息子は、源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の敗北により大和国(奈良県)の吉野まで落ち延びる。
ただ、平氏軍の落武者狩りに伴い、源氏の家族親族も対象となり、そこで平氏軍は御触(おふれ)を出した。
⦅「平治の乱」(へいじのらん)に関わった源氏の一族は出頭しなければ、その身内親族を六条河原で斬首する!⦆
この御触(おふれ)を目にした常盤御前(ときわごぜん/町人→源氏→平氏→藤原氏)と3人の息子は、平安京に戻り六波羅(ろくはら)の平氏の屋敷に自首する。
“京都一番の美女”に目を付けた平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)は、常盤御前(ときわごぜん/町人→源氏→平氏→藤原氏)と3人の息子を引き取る。
この3人の息子が今若(いまわか)こと阿野全成(あのぜんじょう/源氏→平氏)、乙若(おとわか)こと源義円(みなもとぎえん/源氏→平氏)、牛若(うしわか)こと源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)である。
その後も今若(いまわか)は山城国(京都府)の醍醐寺(だいごじ)、乙若(おとわか)は河内国(大阪府)の天王寺(てんのうじ)、牛若(うしわか)こと源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)は山城国(京都府)の鞍馬寺(くらまでら)にそれぞれ預けられた。
この貴船(きふね)の山奥にある鞍馬寺(くらまでら)で牛若(うしわか)こと源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)は、古代イスラエルから来訪した山伏(やまぶし)に扮(ふん)した天狗(てんぐ)に鍛えられ、立派な武者として成長した。
天狗…『源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)よぉ、武道も大切だが、学道はもっと大切である、だから今日はヘブライ語を伝授しよう。』
源義経…『はい、天狗(てんぐ)先生。』
天狗…『ヘブライ語で、神様の聖地はミヤ(宮/みや)、皇族はミカドル(帝/みかど)、皇帝はマクト(尊/みこと)である。』
源義経…『ヤッホーは神様、ヨイショは神様の助命、ワッショイは神様の来訪ですよね。』
天狗…『うむ、よく出来ました。 では次に、古代イスラエルで7月17日に開催される“シオン祭”をこの日本の京都でも開催していますが、それはどんな祭ですか?』
源義経…『はい、天狗(てんぐ)先生、それは7月17日に開催される“祇園祭”です。』
京都の二条城の南側には、神泉苑(しんせんえん)が怨霊退治や疫病封じの場として設けられ、869年に疫神怨霊を鎮める祭礼である御霊会(ごりょうえ)として7月17日に“祇園祭”が開催される様になった。
陸奥国(むつ/岩手県)の奥州平泉では、1159年に第2代奥州藤原氏の藤原基衡(ふじわらもとひら/奥州藤原氏)が死去し、第3代奥州藤原氏の藤原秀衡(ふじわらひでひら/奥州藤原氏)が跡目を継いだ。
藤原秀衡(ふじわらひでひら)は蝦夷(えみし)の女性との間に長男の藤原国衡(ふじわらくにひら/奥州藤原氏)をもうける。
さらに陸奥国司(むつこくし)かつ鎮守府将軍(ちんじゅふしょうぐん)の藤原基通(ふじわらもとみち/公家)の娘を正室として迎入れ、次男となる第4代奥州藤原氏の藤原泰衡(ふじわらやすひら/奥州藤原氏)が生まれる。
また、別の側室とも三男の藤原忠衡(ふじわらただひら/奥州藤原氏)をもうける。
この奥州藤原氏3兄弟が滅亡へと追い込むとは、まだ、知る由(よし)もない。
義父の藤原基通(ふじわらもとみち/公家)は、「平治の乱」(へいじのらん)で源義朝(みなもとよしとも/朝廷→源氏)と共に反乱(クーデター)を起こした藤原信頼(ふじわらのぶより/公家)の弟で、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の報復に戦々恐々としていた。
ただ、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の報復は奥州平泉までは及ばず、逆に第3代奥州藤原氏の藤原秀衡(ふじわらひでひら/奥州藤原氏)の絶大な権力を利用するため鎮守府将軍(ちんじゅふしょうぐん)に任命する。
藤原秀衡(ふじわらひでひら/奥州藤原氏)は、いずれ源氏が復活して“平氏討伐”を計(はか)る事を見越して、奥州藤原氏の間者(かんじゃ/スパイ)でもある陸奥の金商人の金売吉次(かねうりきちじ/商人)を京都の平安京に送り込み、事情調査と情報収集と行わせていた。
そこで畿内(関西)に居る今若(いまわか)、乙若(おとわか)、牛若(うしわか)こと源義経(みなもとよしつね/源氏→藤原)に目を付けて、武将として見込みのある牛若(うしわか)こと源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)を奥州平泉に呼び寄せる。
この道中に源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)に賛同した者が集まり、奥州平泉まで同行する。
近江国(滋賀県)の比叡山にある天台宗(てんだいしゅう)の延暦寺(えんりゃくじ)の僧侶だった武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)。
因(ちな)みに夢を打(ぶ)ち壊す様な事を申し上げますと、源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)と武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)が生きた平安時代末期には、京都の鴨川に五条大橋(国道1号線)はまだ架かっていませんでした。
源義朝(みなもとよしとも/朝廷→源氏)の家臣の鎌田政清(かまたまさきよ/源氏)の甥で鎌田政近(かまたまさちか/源氏)で、正門坊(しょうもんぼう)と言う僧侶でもある。
駿河国(静岡県)と相模国(神奈川県)の山賊だった伊勢義盛(いせよしもり/武士)。
常陸国(茨城県)は香取の常陸坊海尊(ひたちぼうかいそん/僧侶)。
源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)の一行は、平泉に到着すると第3代奥州藤原氏の藤原秀衡(ふじわらひでひら/奥州藤原氏)に謁見(えっけん)し、そこで長男の藤原国衡(ふじわらくにひら/奥州藤原氏)、第4代奥州藤原氏となる次男の藤原泰衡(ふじわらやすひら/奥州藤原氏)、三男の藤原忠衡(ふじわらただひら/奥州藤原氏)の紹介を受ける。
長男の藤原国衡(ふじわらくにひら/奥州藤原氏)と三男の藤原忠衡(ふじわらただひら/奥州藤原氏)は源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)に対して好意的だったが、次男の藤原泰衡(ふじわらやすひら/奥州藤原氏)は反感を剥(む)き出しにする。
奥州藤原氏の館(やかた)でもある“柳の御所”の北側に高館(たかだち)を設け、源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)の住居とした。
源義経(みなもとよしつね/源氏→ 奥州藤原氏)は奥州平泉に1174年〜1180年まで滞在し、この間に“騎馬”や“弓取”などの武術を学ぶ。
この東北地方の経験や訓練が、勇猛果敢な武将としての能力を引き出している。
この頃、第3代奥州藤原氏の藤原秀衡(ふじわらひでひら/奥州藤原氏)は無量光院(むりょうこういん)を建立(こんりゅう)し、京都は宇治市に建つ“平等院鳳凰堂”を模した寺院を配置する。
これにより奥州平泉を中心とした東北地方の極楽浄土(天国)は具現化した事になる。
CONNIE FRANCIS /♪ LIPSTICK ON YOUR COLLAR
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:07:31
◆◇◆其の五十八:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
史実とは違うが、後世に創作された源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)の伝承を見てみる。
幼い牛若(うしわか)は稚児姿(ちごすがた)で可愛らしいかったが、貴船(きふね)の山奥にある鞍馬寺(くらまでら)で山伏(やまぶし)の天狗(てんぐ)先生に、文武を教えられ鍛えられた成果で、立派な武術を身に付けた青年になった。
その時に、源義朝(みなもとよしとも/朝廷→源氏)の家臣の鎌田政清(かまたまさきよ/源氏)の甥で鎌田政近(かまたまさちか/源氏)と出会い、牛若(うしわか)は源氏の家系だと教えられる。
鎌田政近(かまたまさちか/源氏)は僧侶の正門坊(しょうもんぼう)でも活動して、少進坊(しょうしんぼう/僧侶)を名乗っていた可能性もある。
そんな平安京のある夜、平氏の屋敷が軒を連ねる六波羅(ろくはら)に程近い鴨川に架かる五条大橋で、傍若無人(ぼうじゃくぶじん)な平氏の武士を待ち構える大男が居た。
その名は武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)で、“北嶺”(ほくれい)と呼ばれる近江国(滋賀県)にある天台宗(てんだいしゅう)の延暦寺(えんりゃくじ)に配備された僧侶の山法師(やまほうし)だった。
五条楽園(遊郭)で遊んだ帰りの平家武士3人が五条大橋を渡っている。
平家武士A…『平家にあらずんば、落武者の源氏武士に間違いない! アハッハッハッハッ〜』
平家武士B…『驕る平家は、繁栄するぅ〜 いいぞっ、いいぞぉ!』
平家武士C…『祇園精舍(ぎおんしょうじゃ)の鐘の声、諸行無常(しょぎょうむじょう)の響きあり。 娑羅双樹(さらそうじゅ)の花の色、盛者必衰(じょうしゃひっすい)の理をあらはす。 驕(おご)れる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし。 う〜〜ん、良い歌だなぁ〜』
平家武士A…『アホォ、それは平家滅亡を暗示した歌だぞぉ! んっ!? 誰だぁ!?』
武蔵坊弁慶…『わしぃは山法師(やまほうし)の武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)、失礼ながら其方(そなた)達の刀(かたな)を頂きに参った。 この橋に刀(かたな)を置いて帰ってはくれないか?』
平家武士B…『何をぉ〜! 武士の命より大切な刀(かたな)を置いていけだと〜!? 生意気なクソ坊主めぇ〜 驕る平家が叩きのめしてやるわぁい!』
バサッ バサッバサッ
平家武士B…『ギャ〜〜 やられた〜〜』
ゴロン
武蔵坊弁慶…『驕る平家は、五条大橋に首が転がる。』
平家武士A…『うわぁ、ちくしょ〜 仇討(かたきう)ちじゃ〜〜』
バサッ バサッバサッ
平家武士A…『ギャ〜〜 やられた〜〜』
ゴロン
武蔵坊弁慶…『平家にあれば、五条大橋に首が転がる。』
平家武士C…『うわぁわぁわぁ〜』
シャーーー
武蔵坊弁慶…『そこでオシッコを漏らしているお主はどうする?』
平家武士C…『御免なさい、降参します。 刀(かたな)は置いていきますので、命だけはご勘弁下さぁ〜〜い。』
そう言って残った1人の平家武士は逃げていった。
武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)は横柄な平家武士をはじめ、あらゆる武士から刀狩りをして武家の軍力を衰えさせ、僧兵の怖さを思い知らしめていた。
武蔵坊弁慶…『ウワァハッハッハッ〜 これで刀(かたな)は3本も手に入り、合計が999本と、祈願の1000本まであと1本だなぁ!』
ピィ〜ヒョロロ〜 ピィ〜ヒョロロ〜
月夜の平安京に笛の音色が響く。
武蔵坊弁慶…『んっ!? なんじゃお前はぁ!?』
牛若(源義経)…『名乗る程の者でもない。』
武蔵坊弁慶…『こしゃくな小僧だっ! おっ、腰にぶら下げているのは刀(かたな)ではないかぁ! 小僧、その刀(かたな)を置いていけっ!』
牛若(源義経)…『刀(かたな)が欲しければ、自力で奪ったらいい。』
武蔵坊弁慶…『生意気なぁ〜 その言葉を忘れるなぁ〜』
バサッ バサッバサッ
ヒョイ ヒョイヒョイ ヒョイ
武蔵坊弁慶…『うんっ!? 小僧、どこ行ったぁ!?』
牛若(源義経)…『ここだっ、大男よぉ!』
橋の欄干に立つ牛若(うしわか)、再び武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)は薙刀(なぎなた)を振り回す。
バサッ バサッバサッ
ヒョイ ヒョイヒョイ ヒョイ
武蔵坊弁慶…『なぁ、何故(なぜ)に薙刀(なぎなた)が当たらぬかぁ!?』
牛若(源義経)…『お主は力任せに武具(ぶぐ)を振り回しているだけである。 武道とは己と向き合い心で構えるもの。』
そう言って牛若(うしわか)は吹いていた笛で、武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)の脛(すね)を小突(こづ)いた。
コンッ
武蔵坊弁慶…『痛ぁ〜〜い!』
牛若(源義経)…『フハッハッハッハッ〜 これぞ弁慶の泣き所であるなぁ!』
武蔵坊弁慶…『参りました。 貴方のお名前をお聞かせ下さい。』
牛若(源義経)…『私は平氏に滅ぼされた源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)の息子で牛若(うしわか)と申す。』
武蔵坊弁慶…『なぁ、何とぉ! 源氏の棟梁(とうりょう)の御子息であったかぁ! 実はわしぃの刀狩り千本の祈願は、源氏を再興して平氏を討伐する事であった。 今日、その願いが貴方に逢えて叶ったぞぉ!』
こうして武蔵坊弁慶(むさしぼうべんけい/僧侶)は、牛若(うしわか)こと源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)に一生涯を仕えるのであった。
そして牛若(うしわか)も元服(げんぷく)して一人前になる時が来た。
ただ、父親の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は既(すで)に他界しており、他の親族も皆無だった為に、元服(げんぷく)の儀式を自分1人で実施する事になる。
通常は烏帽子親(えぼしおや)から烏帽子(えぼし)を頭に被せられ、姓(かばね)が与えられるが、全てを牛若(うしわか)が1人で行った。
そして名乗って姓(かばね)が源九郎義経(げんくろうよしつね)で、源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)である。
BOB B.SOXX & THE BLUE JEANS /♪ WHY DO LOVERS BREAK EACH OTHERS HEARTS?
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:08:33
◆◇◆其の五十九:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)は奥州は平泉を拠点に東北を統治する第3代奥州藤原氏の藤原秀衡(ふじわらひでひら/奥州藤原氏)に身を寄せていたが、一時、京都の平安京に戻った時。
その平安京の近郊の一条に住む僧侶の鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)が、中国の兵法書で武経七書の1種の“六韜”(りくとう)を所有している噂を聞き付ける。
“六韜”(りくとう)には、中国大陸で戦乱が繰り広げられる度(たび)に編み出される兵法や戦術が記載されていた。
その兵法や戦術を6項目に振り分けて3冊にまとめている。
1巻には“文韜”、“武韜”、2巻には“龍韜”、“虎韜”、3巻には“豹韜”、“犬韜”。
“韜”(とう)は剣や弓などを入れる袋の意味で、よく“虎の巻”と言うがそれは2巻の“虎韜”ことを意味している。
一条にある鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)の屋敷を訪れた源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)は、早速、“六韜”(りくとう)の閲覧をお願いした。
源義経…『先生、僕は日本一に強い武士に成りたいので、お願いですから“六韜”(りくとう)を拝見させて下さい。』
鬼一法眼…『嫌だねぇ〜 ベェ〜〜』
源義経…『ケチなクソ坊主だなぁ〜 其方(そっち)がそんな態度なら、こうなれば奥の手だっ!』
こうして何度も鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)の屋敷に通い、“六韜”(りくとう)の閲覧を嘆願するうちに、鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)の娘と恋仲になる。
そして、平安京の南方にある伏見の名神高速道路の京都南インターに連れて行き、西日本最大級と呼ばれるホテル街に通う様になる。
源義経…『おい、“六韜”(りくとう)を持ってきたか?』
鬼一法眼の娘…『はい、この書物でしょ? 愛(いと)しの貴方の為なら何だってするわぁ。』
源義経…『この“六韜”(りくとう)の各ページをスマートフォンでバシャバシャ撮影して保存し、後から見て習得しよう!』
パシャリ パシャリ
鬼一法眼の娘…『ねぇ〜 そんな古い書物に夢中になるよりも、火照(ほて)った私の身体に夢中になってよぉ〜』
源義経…『分かってる、分かってる、これが終わったら、足腰が立たないくらいの極意戦術を施してやるからなぁ!』
パシャリ パシャリ
鬼一法眼の娘…『あぁ〜〜ん 我慢できなぁ〜い! 早く来てぇ〜〜』
こうして伏見のホテル街に鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)の娘と何度も通う事で、“六韜”(りくとう)を熟読して上級者並みの武道を習得する事ができた。
その副作用で、源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)に身体を開発された鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)の娘は女として目覚め、その後、六条の鴨川の西方に広がる五条楽園(遊郭)の遊女として働く様になる。
鬼一法眼の娘…『義経(よしつね)様に開発されて女の喜びが開花したわぁん! このお仕事は天職よぉん。』
源義経…『俺は“六韜”(りくとう)を習得したし、お前の就職先も斡旋(あっせん)できたし、万事うまくいって、めでたし、めでたし。』
鬼一法眼の娘…『あぁ〜〜ん、ちょいとお兄さ〜ん、寄っていかなぁ〜い? サービスするわぁよん。』
愛娘が“六韜”(りくとう)の持ち出しと、源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)とホテル街に入り浸(びた)っている事を知った鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)は怒り心頭に発した。
鬼一法眼…『あの源氏の小僧めぇ〜 わしぃの大事な娘に手を出しやがってぇ、絶対に許さぁ〜〜ん!』
鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)は弟子の湛海坊(たんかいぼう/僧侶)に、源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)を斬首して五条河原に晒し首(さらしくび)にする様に命じる。
そして五条大橋を渡る源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)の前に、湛海坊(たんかいぼう/僧侶)が立ちはだかる。
源義経…『何だ、お主は?』
湛海坊…『問答無用! 其方(そなた)の首を頂戴する。』
そう言って太刀(たち)を振り上げた湛海坊(たんかいぼう/僧侶)は、源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)に斬り掛かる。
バサッ バサッバサッ
湛海坊…『ギャ〜〜 やられた〜〜』
ゴロン
源義経…『また、つまらぬ者を斬った。』
カチッ
源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)に返り討ちに遭った湛海坊(たんかいぼう/僧侶)の首が五条大橋の床板に転がる。
そして源義経(みなもとよしつね/鎌倉→藤原)は、湛海坊(たんかいぼう/僧侶)の首級(しゅきゅう)を橋の欄干の上に置いて晒し首(さらしくび)とした。
翌日、弟子の湛海坊(たんかいぼう/僧侶)が帰ってこないので、鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)が五条大橋に見に行くと、湛海坊(たんかいぼう/僧侶)の晒し首(さらしくび)を見て驚愕(きょうがく)する。
心が動揺する鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)は、動悸(どうき)を落ち着かせる為に気分転換に五条楽園(遊郭)に行く事にした。
鬼一法眼…『ふぅ〜 此処(ここ)に来たら落ち着いてきたわぁい。 さっ、今日はどのお茶屋の、どんな娘にしようかなぁ〜』
鬼一法眼の娘…『あぁ〜〜ん、ちょいと素敵なおじさまぁ〜、寄っていかなぁ〜い? サービスするわぁよん。 あっ、お父さん! どうして此処(ここ)にぃ〜!?』
鬼一法眼…『おっ、お前ぇ!?』
ドキドキ ドキドキ ドキドキ
バタンッ
鬼一法眼の娘…『おっ、お父さん! 救急車、救急車を呼んでぇ〜 あぁ〜 間に合わないかなぁ〜 霊柩車にチェンジよぉん!』
こうして鬼一法眼(きいちほうげん/僧侶)は、人生の幕を閉じた。
SAM COOKE /♪ ANOTHER SATURDAY NIGHT
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:09:34
◆◇◆其の六十:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
●1165年 《武士の時代》
平安時代の末期、京都の平安京では平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が栄華(えいが)を極める。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)と言えば“強欲”や“強権”のイメージを日本の歴史学は植え付けたが、実際は仏教の信仰心に厚く、政権運営も関係者との調整など慎重に実施していた事が伺える。
武将の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、皇室や公家との繋がりも相手から望んだ事で、藤原氏北家(ほっけ)の様に底無しの“欲望”で奪取(だっしゅ)していた訳ではない。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、1146年に安芸国(あき/広島県)の守護に就任した際に、海に浮かぶ厳島神社を造営して寝殿造りの立派な社殿を建築した。
その後、見事に出世し公家となった平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は感謝に意を表して厳島神社に参拝する。
1160年に平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は武士から公家に昇格し、鴨川沿いに六条周辺の六波羅(ろくはら)に平家系の武士が住む屋敷を5000軒を設けて、此処(ここ)を“六波羅政権”(ろくはらせいけん)として拠点とした。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)は、元は源氏の出生で第40代天皇の天武天皇(てんむてんのう)の系統の高階氏(たかしなうじ)の養子に入った高階基章(たかしなもとあき/源氏→朝廷)の娘を妻に娶(めと)り、嫡男(ちゃくなん)で平氏の家督後継者である平重盛(たいらしげもり/平氏)と次男の平基盛(たいらもともり/平氏)が誕生する。
次男の平基盛(たいらもともり/平氏)は、1156年に起こった「保元の乱」(ほうげんのらん)で上皇軍に就いて処刑された藤原頼長(ふじわらよりなが/公家→上皇)の怨霊により、1162年に山城国(京都府)の宇治川で溺死している。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)の正妻が亡くなり、継室として二位尼(にいのあま)こと平時子(たいらときこ/平氏)を妻に娶(めと)る。
その子供に平宗盛(たいらむねもり/平氏)、平知盛(たいらとももり/平氏)、平徳子(たいらとくし/平氏→朝廷)、平重衡(たいらしげひら/平氏)が誕生する。
娘の平徳子(たいらとくし/平氏→朝廷)は、第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)の妻、第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)の母親となる。
息子は、「源平合戦」(げんぺいかっせん)にて摂津国(兵庫県)の鵯越(ひよどりごえ)こと「一ノ谷の戦」(いちのたにのたたかい)で源氏軍に拘束され捕虜となった平重衡(たいらしげひら/平氏)が、終戦後に木津川の河原で斬首された。
平宗盛(たいらむねもり/平氏)と平知盛(たいらとももり/平氏)、それに母親の二位尼(にいのあま)こと平時子(たいらときこ/平氏)と孫の第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)は、最後の「源平合戦」(げんぺいかっせん)にて長門国(山口県)の1185年に起こった「壇ノ浦の戦」(だんのうらのたたかい)で其々(それぞれ)が人生の幕を降ろした。
ある時、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)の勅命(ちょくめい)により、妻の平滋子(たいらじし/平氏→朝廷)との息子の憲仁親王(のりひとしんのう)を皇太子に就任させる。
平滋子(たいらじし/平氏→朝廷)とは、第77代天皇の後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)の妻で女御(にょうご)で、第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)の母親となり、平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)の妻である平時子(たいらときこ/平氏)の姉妹だった為に、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)の平氏に対する好意が伺われる。
これにはもう1つ理由があり、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷)と、息子の第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)が仲違(なかたが)いをして、親子関係と朝廷では険悪な雰囲気(ムード)が漂っていた。
その為に院政(いんせい)の力で平氏の系統でもある憲仁親王(のりひとしんのう)を皇太子に指名して、後々の第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)となる。
この頃の天皇の皇位の流れを見てみる。
1158年に、第77代天皇の後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)が退位して、息子の第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)が皇位を譲位(じょうい)する。
1165年に、第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)が崩御(ほうぎょ)して、息子の第79代天皇の六条天皇(ろくじょうてんのう/朝廷)が皇位を即位(そくい)する。
1168年に、第79代天皇の六条天皇(ろくじょうてんのう/朝廷)が退位して、後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷)の息子の第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)が皇位を譲位(じょうい)する。
1180年に、第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)が退位して、息子の第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)が7歳で皇位を譲位(じょうい)する。
1165年に平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は第77代天皇だった後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)の屋敷の敷地内に、近江国(滋賀県)の比叡山に建つ延暦寺(えんりゃくじ)が総本山の天台宗(てんだいしゅう)の寺院として蓮華王院本堂(れんげおういんほんどう)こと三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)を建立(こんりゅう)して寄贈した。
三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)の実際の幅員は、一間は1.8mで柱間隔が二間ある為に3.6mの33を掛けると118.8mの六十六間ある。
だから名称は寸法の間(げん)ではなく、間隔の事を意味している事が解る。
因みに、この端から端までの距離の長い三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)では、昔から弓矢の正確さを競う“通し矢”と言う競技が行われている。
しかし、選手の中には弓矢が下手な者も居り、逸れた矢が三十三間堂(さんじゅうさんげんどう)に突き刺さり、今でも傷が残っていると言う。
平清盛…『アホォかお前らはぁ! どっか他でやれやぁ!』
SHA-NA-NA /♪ ROCK 'N' ROLL IS HERE TO STAY
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:10:33
◆◇◆其の六十一:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
1165年に、第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)が崩御(ほうぎょ)し、息子の第79代天皇の六条天皇(ろくじょうてんのう/朝廷)が皇位を即位(そくい)している。
これにより平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が太政大臣に就任する。
この頃は、平氏が最も繁栄を極めた時期でもある。
平家の棟梁(とうりょう)でもある武将としての平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)は、平氏軍を源氏軍の様な強靭で実直な武家集団の組織力と結束力を目指していた。
ところが源氏軍との決定的な違いは、その家臣や平氏武士の士気の低さにあった。
“苦しい道”と“楽な道”があれば、源氏軍の武士は“苦しい道”を選択して邁進(まいしん)するが、平氏軍の武士は“楽な道”を選択して怠(なま)ける。
日本各地の戦地に赴(おもむ)き戦ってきた源氏軍と、平安京の守衛や防御を担っていた平氏軍であるので、戦(いくさ)に対する心構えが違い、戦力差から仕方ない部分もある。
例えるなら、源氏軍は国防軍隊、平氏軍は首都警備隊とでも言うべきか。
此処(ここ)から解る通りに「源平合戦」(げんぺいかっせん)では、『逃げる平氏に、追う源氏。』の構図となっている。
そこから飛び出した言葉が、これだっ!
平時忠…『平家にあらずんば、人にあらず。』⦅平家出身でない者は、人非人(にんぴにん/人で無し)である。⦆
平清盛…『アホォ! お前がそんな事を言うから800年後に日本の歴史で、何でも成功を治める慢心(まんしん)したわしぃが言った様に未来の日本人に思われてるやぁないかぁ!』
平時忠(たいらときただ/朝廷)とは、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の妻の平時子(たいらのときこ/朝廷)の弟にあたる。
この平時忠(たいらときただ/朝廷)の発言が瞬く間に平安京を駆け巡り、平氏に対して武士を見下す公家の反感を買う。
1168年に、第79代天皇の六条天皇(ろくじょうてんのう/朝廷)が崩御(ほうぎょ)し、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)の息子で平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の甥の第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)が皇位を即位(そくい)する。
この頃に院政(いんせい)を敷いていた後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)は、出家して後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)に就く。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は病気を発症して太政大臣を辞任し、住居を京都の六波羅(ろくはら)から、摂津国(兵庫県)の福原(ふくはら)に移転するが、ここから朝廷の政権運営を指揮した。
1172年に平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の娘の平徳子(たいらとくし/平氏→朝廷)が、第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)の側室となり、後に第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)が誕生する。
ただ、この平氏の権力集中に対して平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の同友の後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)は危惧(きぐ)し始めた。
そこに公家の藤原房前(ふじわらふささき/公家)の北家(ほっけ)で大納言に就いていた藤原成親(ふじわらなりちか/公家)、元は村上源氏で僧侶になった俊寛(しゅんかん/源氏→僧侶)、同じく藤原房前(ふじわらふささき/公家)の北家(ほっけ)で僧侶になった西光(さいこう/藤原→僧侶)により、平安京では“平氏討伐”の動きが強まる。
LITTLE FEAT /♪ RAD GUMBO
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:11:41
◆◇◆其の六十二:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
●1177年 《武士の時代》
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の権力集中に対して、後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)をはじめ、多くの公家や僧侶が危機感を募(つの)らせていた。
ある夜、東山の山中の鹿ヶ谷(ししがたに)にある高貴な僧侶だった俊寛(しゅんかん/源氏→僧侶)の別荘で宴会が開催されていた。
その宴会に参加していたのは、院政(いんせい)の実権を握る後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)、公家の藤原房前(ふじわらふささき/公家)の北家(ほっけ)で大納言に就いていた藤原成親(ふじわらなりちか/公家)、藤原房前(ふじわらふささき/公家)の北家(ほっけ)で僧侶になった西光(さいこう/藤原→僧侶)、村上源氏で僧侶になった俊寛(しゅんかん/源氏→僧侶)、摂津源氏の系統の多田源氏の源行綱(みなもとゆきつな)こと多田行綱(ただゆきつな/源氏)の面々だった。
俊寛…『最近の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の権力掌握や平氏軍の横柄(おうへい)な振る舞いは目に余るでごじゃる。』
後白河法皇…『う〜〜ん、確かになぉ〜 昔は平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)との関係も上手くいっていたのになぁ〜』
西光…『そりゃ、あれだけの権力と財力を手にすれば、天照大御神(アマテラス)でも、御釈迦様(仏陀)でも、慢心(まんしん)するでごじゃるよぉ。』
藤原成親…『確か、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は重病を克服した後に出家して僧侶の身分ではないかぁ? そんなお坊さんが権力と武力で平安京をはじめ、日本全国を統治しているとは世も末(すえ)であるなぁ〜 お酒を呑まずにはおれんぞぉ! おっとっと〜』
コロン トクトクトク
藤原成親(ふじわらなりちか/公家)がお酒の瓶子(へいし)こと徳利(とくり/銚子)を持とうとしたところ、瓶子(へいし)こと徳利(とくり/銚子)が転がってお酒が畳に流れ出た。
多田行綱…『おっ、瓶子(へいし)が倒れたぞっ! これは光明(こうみょう)であり、今こそ“平家打倒”すべきだっ!』
これを見た参加者は大喜びして、源行綱(みなもとゆきつな)こと多田行綱(ただゆきつな/源氏)の“平家打倒”に賛同する。
これを1177年に起こった「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)と呼ぶ。
この頃、僧侶の西光(さいこう/藤原→僧侶)の息子である藤原師高(ふじわらもろたか/公家)が、加賀国(石川県)の国司(こくし)に就任したが、自分は着任せず代理人に就かせる遙任(ようにん)とした。
その代理人を弟の藤原師経(ふじわらもろつね/公家)が目代(もくだい)として、夏の暑い日に加賀国(石川県)に出向いた。
この加賀国(石川県)の地域は古くから越前国(福井県)、飛騨国(岐阜県)、信濃国(長野県)の飛騨山脈(北アルプス)や木曽山脈(中央アルプス)の山々に隔てられた神聖な領域とされていた。
そんな加賀国(石川県)と越前国(福井県)と飛騨国(岐阜県)の国境に2700mの白山(はくさん)が鎮座しており、この周辺の領民は“山岳信仰”(さんがくしんこう)の対象として毎朝毎夕に必ず拝んでいる。
この加賀国(石川県)の白山(はくさん)を御神山として、笥笠中宮神社(けがさちゅうぐうじんじゃ/白山)の中宮 (ちゅうぐう)、佐良早松神社(さらはやまつじんじゃ/白山)の佐良宮 (さらのみや)、白山別宮神社(しらやまべっくうじんじゃ/白山)の別宮(べっくう)の三社(さんじゃ)と、護国寺、昌隆寺、松谷寺、蓮花寺、善興寺、長寛寺、涌泉寺(うせんじ)、隆明寺の八院(はちいん)で、“白山三社八院”(はくさんさんじゃはちいん)と呼んでいた。
そんな白山(はくさん)の麓(ふもと)に位置する鵜川(うかわ)に、八院(はちいん)の白山末寺である涌泉寺(うせんじ)が建っていた。
この涌泉寺(うせんじ)に隣接した秘湯に浸かって汗を流していた僧侶達を、加賀国(石川県)の目代(もくだい)に就いた藤原師経(ふじわらもろつね/公家)の御一行が通り掛かり、気持ち良さそうに温泉に浸かる僧侶を発見する。
夏の暑い日でもあり、自分達も温泉に失礼して浸からせてもらいたいと思うのが人情である。
藤原師経…『おいっ、坊主! 俺達にも温泉に浸からせろっ!』
僧侶…『お前、口の利き方を分かってない様だな! 此処(ここ)は神聖なる白山(はくさん)の聖域(サンクチュアリ)、お主ら役人が来る処(ところ)では無いわぁい!』
藤原師経…『生意気なクソ坊主だなぁ! 俺を誰だと知っての無礼な対応かっ!』
僧侶…『山の猿(サル)とも見分けがつかぬお主らを、知っている筈(はず)がないわぁい!』
藤原師経…『サッ、サルゥ〜!? クッソォ〜 覚えておけっ!』
これがキッカケで「鵜川合戦」(うかわかっせん)が勃発した。
初戦は白山(はくさん)の山中で武術の修行を積んだ僧兵の仏教軍により、都会育ちのひ弱な藤原師経(ふじわらもろつね/公家)が率いる朝廷軍は惨敗した。
都会育ちの歪(ゆが)んだ思考を持つ藤原師経(ふじわらもろつね/公家)は、悔しさ百倍で報復に出て、何と仏の道を教え極楽浄土(ごくらくじょうど)と言われる黄泉の国(よみのくに/天国)に導く寺院の涌泉寺(うせんじ)に火を放ち全焼させたのである。
これに激怒したのが御神山の白山(はくさん)に宿(やど)り祀(まつ)られる神々である。
神様の一言で北陸から信州に至る仏教信者が仏教軍を結成して、加賀国(石川県)の目代(もくだい)の藤原師経(ふじわらもろつね/公家)を襲撃する為に押し寄せて来た。
これにビビった藤原師経(ふじわらもろつね/公家)は、北陸新幹線の小松駅から飛び乗り越前国(福井県)の敦賀駅で下車して、JRに乗り換えて特急のサンダーバード(雷鳥)で京都駅まで行って平安京の大内裏(だいだいり)に逃げ込んだ。
Gary Lewis & The Playboys/♪ COUNT ME IN
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:12:40
◆◇◆其の六十三:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
『逃げる藤原氏に追う仏教。』
同じルートで仏教軍も侵攻し、琵琶湖が見えてきた処(ところ)で途中下車して、近江国(滋賀県)の比叡山に建つ天台宗(てんだいしゅう)の延暦寺(えんりゃくじ)に立ち寄り、“藤原師経討伐”(ふじわらもろつねとうばつ)に対して仏教軍への参戦を呼び掛けた。
これを快諾した延暦寺(えんりゃくじ)の僧兵も加わり、比叡山から大所帯となった仏教軍が平安京に雪崩(なだ)れ込んできた。
これを「仏教比叡おろし」と呼ぶ。
これに対して朝廷も平氏に挙兵を呼び掛けて朝廷軍を結成して、平安京の防御と守護を任せた。
平安京の大内裏(だいだいり)の北方を清和源氏の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が率いる朝廷軍源氏隊に任せて、東南西方を平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の息子で総大将の平重盛(たいらしげもり/平氏)が率いる朝廷軍平氏隊が布陣した。
源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)とは、1160年に起こった「平治の乱」(へいじのらん)で源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)を裏切り、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)に就いた源氏でありながら平氏に味方した人物である。
仏教軍は、大内裏(だいだいり)の陣営を見て、一番に防御力の弱い北方の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が率いる朝廷軍源氏隊に侵攻した。
神輿(みこし/しんよ)を担いで軍備を搭載した仏教軍が押し寄せて来る。
此処(ここ)で八幡太郎(はちまんたろう)こと源義家(みなもとよしいえ/朝廷)を筆頭に武家の名門家でもある清和源氏の血が漲(みなぎ)る源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が採った行動とは!?
僧兵…『えぇ〜い! この門を開けぇ〜〜い!』
源頼政…『ゴメンなさぁ〜〜い、私が悪(わる)う御座いました。 源氏は古(いにしえ)から仏教に感銘を受けて崇拝している家系です。 あなた方に敵対するつもりは毛頭(もうとう)ありません。』
僧兵…『なんじゃ、お前は!? 戦わずして直(す)ぐに降参かぁ?!』
源頼政…『はい、ですから、仏教を蔑(ないがし)ろにして敵意剥き出しの朝廷軍平氏隊が守護する門から御攻(おせ)め下さい。』
僧兵…『お主みたいな腑抜けを相手してもしょうがない。 別の門に討ち入るぞっ!』
源頼政…『ホッ、助かったぁ!』
仏教軍は、大内裏(だいだいり)の東方に移動して、そこに布陣する平重盛(たいらしげもり/平氏)が率いる朝廷軍平氏隊に対して、神輿(みこし/しんよ)を前面にして仏教軍が侵攻する。
僧兵…『まさか神様が宿る神輿(みこし/しんよ)を攻撃はできないだろう!』
平重盛…『弓矢部隊の兵士よっ、全員、矢を放てぇ〜』
ギュ〜〜 ビューーー
ズバンッ
朝廷軍平氏隊の弓矢部隊から射られた何本の矢が神輿(みこし/しんよ)に突き刺さり、僧兵達も倒れていく。
僧兵…『えっ!? 神様やぁでぇ? 恐ろしくなぁいんかぁい?!』
平重盛…『戦(いくさ)となれば神も仏もあるかぁいなぁ! そんなもぉん、怖がって斬った斬られたの戦(いくさ)ができるかぁい!』
僧兵…『ヤベェ、仏教軍は全員撤収! 全員撤収ぅ〜〜!』
この時の平重盛(たいらしげもり/平氏)が率いる朝廷軍平氏隊は、以前の様な平氏の軍隊とは違い、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が組成した特殊部隊によって鍛えられた武士団であった。
この特殊部隊をHAT(ヘイシ・アサルト・チーム)と名付けられた。
GARY PUCKETT & THE UNION GAP /♪ YOUNG GIRL
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:13:39
◆◇◆其の六十四:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
この平氏が組成した特殊部隊のHAT(ヘイシ・アサルト・チーム)は、平安京をはじめ日本全国にその名を轟(とどろ)かせた。
これを知った「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)の首謀者でもある源行綱(みなもとゆきつな)こと多田行綱(ただゆきつな/源氏)は驚愕(きみょうがく)する。
多田行綱…『ヤベェなぁ〜 あの“平家打倒”の計画が平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)に知れたら、間違いなく命は無いなぁ〜 こうしゃおれんっ!』
そう言って平氏別邸の西八条第(にしはちじょうてい/梅小路)に移り住んでいた平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の元を訪ねた。
多田行綱…『親王(しんおう)に拝謁(はいえつ)致します。』
平清盛…『親王(しんおう)? わしぃは親王(しんおう)に就いたつもりはないぞっ! そんな口先だけのおべんちゃらを言う奴が、もっとも信用に置けん。』
多田行綱…『いやぁ、いやぁ、今日は重大なお話しが在りまして、実は後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)を筆頭に、公家の藤原成親(ふじわらなりちか/公家)と僧侶の西光(さいこう/藤原→僧侶)と俊寛(しゅんかん/源氏→僧侶)が平氏政権に対して謀反(むほん)を企てております。』
平清盛…『なぁ、なんやてぇ〜!? あの野郎ぅ〜 平氏全軍で先制攻撃を喰らわしてみせるわぁい!』
多田行綱…『私は平氏の僕(しもべ)です。 今後共に御用命を何なりとお申し付け下さい。』
平清盛…『お主の顔を見てると虫唾(むしず)が走るわぁい! 貴様の様な卑怯者(ひきょうもの)は生まれ故郷の摂津国(大阪府)に帰って糞(クソ)して寝てろっ!』
多田行綱…『はぁは〜〜』
ここで平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)に大きな問題が発生する。
平氏の家督を引き継ぐ嫡男(ちゃくなん)である平重盛(たいらしげもり/平氏)の妻の藤原経子(ふじわらけいし/公家→平氏)が、“平家打倒”の計画の主要メンバーの藤原成親(ふじわらなりちか/公家)だった。
そこで平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、平氏別邸の西八条第(にしはちじょうてい/梅小路)に藤原成親(ふじわらなりちか/公家)を招待してはりはり鍋(鯨鍋)を振る舞い、お腹も一杯になったところで近所の島原遊郭に行って、角屋(すみや/揚屋)でお酒を汲(く)み合わしながら、輪違屋(わちがいや/置屋)からお気に入りの吉野桜太夫(よしのさくらたゆう)を呼んだ。
吉野桜太夫…『いやぁ〜 清盛(きよもり)はぁん、お久しぶりやぁないのぉ? うちぃと言う女が居(い)てぇるのに、何処(どこ)ぞぉでぇ浮気しとったんちゃう?』
平清盛…『いゃ〜 ゴメン、ゴメン、朝廷やら、仏教やら、源氏やらの対応で何かと忙しくて、なかなか来れなかったんよぉ。』
吉野桜太夫…『あらっ? 此方(こちら)のお兄さんは新顔ねぇ〜』
藤原成親…『あっ、親族の藤原成親(ふじわらなりちか)と申します。 宜しく御願い致します。』
吉野桜太夫…『いゃ〜 藤原氏きっての立派な御子息ねぇ〜 うちぃ、惚(ほ)れてまぁうわぁ。』
平清盛…『おいおい、この青年は既婚者で愛妻にちゃんと手綱(たずな)を握られているぞぉ。』
吉野桜太夫…『あらぁ、残念!』
藤原成親…『ところで今日は、私に何か用事があるのでしょうか?』
平清盛…『いやぁなにぃ、たまには息子の義兄とも交流を深めたいと思ってなぁ〜 特に用事も理由も無いんやぁ〜』
吉野桜太夫…『清盛(きよもり)はぁんの、こう言う白(しら)を切る時が一番に怖いねぇんでぇ! お兄さんも気を付けなはぁれぇ。』
平清盛…『おいおい、若い青年を脅してどうする! なぁ〜 成親(なりちか)君。』
藤原成親…『・・・』
吉野桜太夫…『わてぇの予感はよぉ〜当たるでぇ〜』
その間に、平氏軍の特殊部隊のHAT(ヘイシ・アサルト・チーム)が西光(さいこう/藤原→僧侶)を拘束し、四条大宮の近くの壬生(みぶ)に建つ前川邸にある東の蔵で拷問して「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)の全容(ぜんよう)を聞き出した。
平氏武士…『貴様、これでも白状せぬかぁ!』
西光…『ぎやぁ〜〜 やめてぇ〜〜』
西光(さいこう/藤原→僧侶)は亀甲縛りで天井に吊るされて、鞭(ムチ)で打たれて、赤い大きな蝋燭(ロウソク)で炙(あぶ)られた。
平氏武士…『なかなかしぶとい奴やぁのぉ、もっと鞭(ムチ)で強く打つかぁ!』
ビシッ ビシッ ビシッ ビシッ
西光…『いやぁ〜〜 イクゥ〜〜』
シャ〜〜〜
平氏武士…『おい、此奴(こやつ)、苦痛じゃなく感じているぞぉ!』
西光…『あぁ〜〜 止めないでぇ〜 何でも話しますから、もっとキツイのを御願い。』
平氏武士…『わしぃらの思惑とはちょっと違ったが、一応は白状したなぁ。』
こうして西光(さいこう/藤原→僧侶)が「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)の全貌(ぜんぼう)を話した事で、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が迅速(じんそく)に動く。
この後、西光(さいこう/藤原→僧侶)は五条の朱雀大路(すざくおおじ)に連行されて斬首され、家族一族も斬殺された。
Thurston Harris /♪ Little Bitty Pretty One
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:14:40
◆◇◆其の六十五:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の次の標的者(ターゲット)は、息子の平重盛(たいらしげもり/平氏)の妻の藤原経子(ふじわらけいし/公家→平氏)の兄である藤原成親(ふじわらなりちか/公家)だった。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が公開処刑の準備に取り掛かっている時に、その噂を聞き付けた平重盛(たいらしげもり/平氏)が、父親の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の元に現れる。
平重盛…『父上、誤ってはならぬ! 藤原成親(ふじわらなりちか/公家)に邪(よこしま)な考えがあったにしろ、実行していないではないか! 義兄はれっきとした僕の親族であり、父上と同じ家族の一員なんです。』
平清盛…『息子よぉ、わしぃが許せないのは謀反(むほん)の事では無いわぁい! 藤原成親(ふじわらなりちか/公家)は、島原遊郭でわしぃのお気に入りの吉野桜太夫(よしのさくらたゆう)を寝取りやがった事だっ!』
平重盛…『父上だって妻や子供が居ながら、木屋町の女郎サロン“ミルクパイ”に通い詰めて、オッパイパフパフしているではありませんか!』
平清盛…『うぅ〜ぐっぐっぐっ〜 わしぃの痛い所を突きよってぇ〜』
こうして優秀で武術にも長(た)けた平重盛(たいらしげもり/平氏)により論破され、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、藤原成親(ふじわらなりちか/公家)の公開処刑を中止して、備前国(岡山県)へ流罪となったが、結局はそこで平氏の影の軍団に暗殺されている。
ただ、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の報復はこれで終わらず、次の標的者(ターゲット)は後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)で、七条(しちじょう)の東方に建つ院政(いんせい)を司っていた御所の法住寺殿 (ほうじゅうじどの)から、伏見の桂川近くに建つ鳥羽離宮に移住させて監禁する計画を企てた。
ところがまたも、その噂を聞き付けた平重盛(たいらしげもり/平氏)が、父親の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の元に現れる。
平重盛…『父上、今の山城政権を運営しているのは平氏かも知れませんが、表面上でも院政(いんせい)は継続しており、後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)を監禁すれば朝廷だけでなく、日本全国の朝敵になりますぞぉ!』
平清盛…『何を言うかぁ息子よぉ! 院政(いんせい)なんてとっくに消滅して、山城政権どころか、山城国(京都府)で政権運営を司(つかさど)っている平氏政権が実態であり、事実ではないかぁ!』
平重盛…『では、千年後の日本の歴史の教科書に、平安時代で活躍した武将の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、皇族の後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)を監禁した、前代未聞の大悪党と記載されても良いのですか?』
平清盛…『未来の歴史書物にぃ!? うぅ〜ぐっぐっぐっ〜 それは困る!』
またも、こうして優秀で武術にも長(た)けた平重盛(たいらしげもり/平氏)により論破され、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)の監禁を中止したが、その後の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)と後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)の関係は悪化の一途を辿(たど)り、いよいよ「源平合戦」(げんぺいがっせん)の前兆となる。
「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)に関わった当事者やその家族一族、それに関係者は全て粛清(しゅくせい)され、俊寛(しゅんかん/源氏→僧侶)は流刑となり、その他の者も死罪か流罪となっている。
THE DRIFTERS /♪ THERE GOES MY BABY
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:15:36
◆◇◆其の六十六:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
●1179年 《武士の時代》
平重盛…『この小松内府はいみじく心うるはしくて、父入道(ちちにゅうどう)が謀反心(むほんしん)あるとみて、“とく死なばや”など、云(い)ふと聞こえしに、いかにしたりけるにか、父入道(ちちにゅうどう)が教えにはあらで、不可思議の事を一つしたり。』⦅親父の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は反逆者に成り下がったので、息子の俺は恥辱(ちじょく)に耐えれそうもないから死にてぇ〜⦆
この言葉は、鎌倉時代初期に天台宗(てんだいしゅう)の僧侶で歌人だった慈円(じえん/僧侶)が著書した“愚管抄”(ぐかんしょう)に記述されていた一節である。
慈円(じえん/僧侶)とは、藤原忠通(ふじわらただみち/公家→天皇)の息子で藤原氏北家(ほっけ)の五摂家(ごせっけ)の九条家となり、天台宗(てんだいしゅう)の僧侶で歌人でもある。
天下取りとなった平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)と、文武両道で有能優秀な嫡男(ちゃくなん)の平重盛(たいらしげもり/平氏)の関係は、何処(どこ)で歯車が狂い始めたのか?
此(こ)れには単なる親子関係だけでなく、伊勢平氏の嫡流(ちゃくりゅう)まで遡(さかのぼ)る深い縁がある。
平安時代の中期、第50代天皇の桓武天皇(かんむてんのう/朝廷)の孫である上野国(こうずけ/群馬県)の国司(こくし)に就いた平高望(たいらたかもち/朝廷)が桓武平氏の祖となった。
その息子には平良将(たいらよしまさ/朝廷)と平国香(たいらくにか/朝廷)などが居た。
平良将(たいらよしまさ/朝廷)の息子が勇猛果敢な“武士の祖”と言われる平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)である。
一方、平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)と対立した平国香(たいらくにか/朝廷)の息子が、平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)を討った平貞盛(たいらさだもり/朝廷)で、この後、平安京の朝廷の恩賞により大きく躍進した。
その平貞盛(たいらさだもり/朝廷)の息子が伊勢平氏の祖と言われる平維衡(たいらこれひら/伊勢平氏)で、伊勢国(三重県)の伊勢神宮の領域でもある神郡(しんぐん)にて、親族で坂東平氏の系統の平致頼(たいらむねより/坂東平氏)と対立して合戦を繰り広げる。
神聖なる天照大御神(アマテラス)が治める伊勢国(三重県)の地を血で穢(けが)し、これに平安京の朝廷は激怒して、平維衡(たいらこれひら/伊勢平氏)は謝罪した為に淡路国(兵庫県)に領地移転の転封(てんぽう)となり、謝罪しなかった平致頼(たいらむねより/坂東平氏)は讃岐国(香川県)に流刑となった。
また同じ頃、平将門(たいらまさかど/朝廷→常陸)の孫の平忠常(たいらただつね/房総平氏)が千葉軍を率いて東国で反乱を起こして、藤原道長(ふじわらみちなが/公家)に仕える“道長四天王”と呼ばれる源頼信(みなもとよりのぶ/朝廷)と、息子の源頼義(みなもとよりよし/朝廷)が率いる朝廷軍に進撃され敗北して、平忠常(たいらただつね/房総平氏)の千葉軍だった一味が伊勢国(三重県)に逃亡している。
この事から伊勢国(三重県)には多くの平氏が居住する様になった。
その1人が坂東平氏の庶流(しょりゅう)で伊勢平氏の平正盛(たいらまさもり/朝廷)である。
播磨国(はりま/兵庫県)の国司(こくし)に就いていた藤原氏北家(ほっけ)の魚名流で歌道の六条藤家の祖でもある藤原顕季(ふじわらあきすえ/公家)の家臣として平正盛(たいらまさもり/朝廷)は仕えていた。
4年間の国司(こくし)の任期を終えて藤原顕季(ふじわらあきすえ/公家)は平安京に戻り、第72代天皇だった白河上皇(しらかわじょうこう/朝廷)による院政(いんせい)に勤める院近臣(いんのきんしん)に就任する。
この時に藤原顕季(ふじわらあきすえ/公家)は、気が合い寵愛(ちょうあい)した平正盛(たいらまさもり/朝廷)も平安京に同行させ、後鳥羽上皇(ごとばじょうこう/朝廷)にも謁見(えっけん)して紹介した。
その後、平正盛(たいらまさもり/朝廷)が因幡国(いなば/鳥取県)の国司(こくし)に就いていた頃に、九州で乱暴者の源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)が、肥前国(長崎県)の海域に浮かぶ対馬(つしま)の島々の守護を就いていた時に、九州一帯で略奪を繰り返していた。
朝廷は略奪罪や窃盗罪などで源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)を讃岐国(香川県)への流罪を命じたが、源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)はそれを無視して出雲国(島根県)に逃亡して、そこでも悪事を働いていた。
そこで朝廷は父親の八幡太郎(はちまんたろう)こと源義家(みなもとよしいえ/朝廷)に対して、“親権保護責任”として息子の源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)を征伐する様に命じるも、父親の八幡太郎(はちまんたろう)こと源義家(みなもとよしいえ/朝廷)は出陣する前に亡くなってしまう。
仕方ないので、朝廷は出雲国(島根県)に近い因幡国(いなば/鳥取県)の国司(こくし)だった平正盛(たいらまさもり/朝廷)を代わりに、源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)を征伐するよう依頼し、平正盛(たいらまさもり)は悪党の源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)を始末する。
源義親(みなもとよしちか/朝廷→対馬)の首級(しゅきゅう)は朝廷に献上され、褒美(ほうび)をたんまりと頂戴した平正盛(たいらまさもり/朝廷)はこの後、大出世を果たしていく。
DUSTY SPRINGFIELD /♪ DON'T LET ME LOSE THIS DREAM
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:16:34
◆◇◆其の六十七:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
平正盛(たいらまさもり/朝廷)と藤原顕季(ふじわらあきすえ/公家)、それに1087年の第72代天皇だった白河上皇(しらかわじょうこう/朝廷)、1129年の第74代天皇だった鳥羽上皇(とばじょうこう/朝廷)、1158年の第77代天皇だった後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)の関係性が、今後に大きく影響してくる。
伊勢平氏の平正盛(たいらまさもり/朝廷)の息子が平忠盛(たいらただもり/朝廷→平氏)である。
その息子が平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)である。
その息子が主役の平重盛(たいらしげもり/平氏)である。
一方の院近臣(いんのきんしん)の藤原顕季(ふじわらあきすえ/公家)の息子が藤原家保(ふじわらいえやす/公家)である。
その息子が藤原家成(ふじわらいえなり/公家)である。
その息子が藤原成親(ふじわらなりちか/公家)で、娘が藤原経子(ふじわらけいし/公家→平氏)である。
主役の平重盛(たいらしげもり/平氏)と藤原経子(ふじわらけいし/公家→平氏)は結婚して、此処(ここ)で繋がる。
平正盛(たいらまさもり/朝廷)と藤原顕季(ふじわらあきすえ/公家)の結び付きが平氏の繁栄に導いたが、しかし、その結び付きをもって平氏は滅亡していく。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)と後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)だが、1156年に起こった「保元の乱」(ほうげんのらん)では同盟して共に戦った戦友で良好な関係となり、1160年に起こった「平治の乱」(へいじのらん)でも皇族救出作戦が成功して固い絆(きずな)で結ばれたが、1177年に起こった「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)にて平氏打倒が発覚して友情に亀裂が入る。
この父親と君主や時代に翻弄(ほんろう)され苦悩したのが主役の平重盛(たいらしげもり/平氏)で、強い重い重圧(プレッシャー)から病気を発症して寝込む日々が続き、愛する妻の藤原経子(ふじわらけいし/公家→平氏)の献身的な看病の甲斐(かい)も無く、1179年に人生の幕を閉じる。
この平重盛(たいらしげもり/平氏)の死に心痛めたのが、父親の平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)で嘆(なげ)き哀しみ精神的にも追い込められ、この後から奇行に愚策や悪政が見られる様になる。
此(こ)れにより、我が世の春を謳歌する平氏の歯車が狂い始める。
愛する息子の平重盛(たいらしげもり/平氏)が亡くなる前後の出来事では、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の立場はどうなっていたのか?
1165年に、第78代天皇の二条天皇(にじょうてんのう/朝廷)が崩御(ほうぎょ)し、息子の第79代天皇の六条天皇(ろくじょうてんのう/朝廷)が皇位を即位(そくい)している。
これにより平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が太政大臣に就任する。
1168年に、第79代天皇の六条天皇(ろくじょうてんのう/朝廷)が崩御(ほうぎょ)し、後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)の息子で平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の甥の第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)が皇位を即位(そくい)する。
この頃に院政(いんせい)を敷いていた後白河上皇(ごしらかわじょうこう/朝廷→天皇)は、出家して後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)に就く。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は病気を発症して太政大臣を辞任し、住居を京都の六波羅(ろくはら)から、摂津国(兵庫県)の福原(ふくはら)に移転するが、此処(ここ)から朝廷の政権運営を指揮した。
1172年に平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の娘の平徳子(たいらとくし/平氏→朝廷)が、第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)の側室となり、後に第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)が誕生する。
1179年に息子の平重盛(たいらしげもり/平氏)が亡くなる。
此(こ)れにより後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)は、平重盛(たいらしげもり/平氏)が守護していた越前国(福井県)の領土を領地没収の改易(かいえき)にした。
後白河法皇…『死人に土地無しやぁ!』
更(さら)に院政(いんせい)の院宣(いんぜん)により、朝廷の役人は平氏との繋がりが薄い公家を昇格させて、平氏との結び付きが強い公家を降格させる人事を断行した。
後白河法皇…『平氏の老兵は死なず、ただ消え去るのみやぁ!』
平清盛…『この野郎ぅ〜 息子の土地を奪った挙句(あげく)に、平家一門を平安京から排除するとは何事かぁ〜〜!』
こうして摂津国(兵庫県)の福原(ふくはら)に居た平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、息子の平宗盛(たいらのむねもり/平氏)に命じて1万人の平氏軍を引き連れて京都の平安京に進軍したのである。
平氏軍に包囲された平安京では、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の伝令(でんれい)により朝廷の摂関政治の役職を刷新(さっしん)し、関白や左大臣に右大臣などの藤原氏は全員が罷免(ひめん)された。
平清盛…『平安京は平氏政権の樹立じゃ〜!』
不穏(ふおん)な動きを見せた後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)に対しても、院政(いんせい)が置かれていた法住寺殿 (ほうじゅうじどの)を包囲して拘束し、連行して伏見の鳥羽離宮に幽閉し、圧力を掛けて二度と朝廷の政権運営に口出し出来ない様にした。
これで白河上皇(しらかわじょうこう/朝廷)が始めた院政(いんせい)は終了する事になる。
これを1179年に起こった「治承三年の政変」(じしょうさんねんのせいへん)と呼ぶ。
そして1180年に平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の画策(かくさく)により、第80代天皇の高倉天皇(たかくらてんのう/朝廷)から、息子の第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)に皇位を譲位(じょうい)させた。
それに反発する公家や武将も大勢いた。
DARLENE LOVE /♪ (TODAY I MET)THE BOY I'M GONNA MARRY
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:17:31
◆◇◆其の六十八:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
●1180年 《武士の時代》
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が政権運営を担う朝廷に反発する多くの公家や武将。
そんな時に、平氏の家督後継者だった平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の嫡男(ちゃくなん)だった平重盛(たいらしげもり/平氏)が急死して、平宗盛(たいらむねもり/平氏)が義兄の意志と権利を引き継ぐ事になる。
そして、不穏な空気が漂(ただよ)う平安京にも日常的な時間が流れ、ある時の平宗盛(たいらむねもり/平氏)は、源仲綱(みなもとなかつな/朝廷→源氏)が所有する名馬の木の下(このした)の噂(うわさ)を聞き付ける。
そこで平宗盛(たいらむねもり/平氏)は源仲綱(みなもとなかつな/朝廷→源氏)に対して名馬の木の下(このした)を屋敷まで連れて見せる様に伝令(でんれい)を出す。
ただ、源仲綱(みなもとなかつな/朝廷→源氏)も名馬の木の下(このした)を見たければ、飼育している馬小屋まで見に来いと言う思いがある。
その横暴な平氏に対する鬱積(うっせき)した心情を源仲綱(みなもとなかつな/朝廷→源氏)は、父親の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)に吐露(とろ)する。
源仲綱…『ほぉんまぁムカつくわぁ〜 平宗盛(たいらむねもり/平氏)の奴めぇ〜 馬が見たければ自分でコッチ来いやぁ!』
源頼政…『お前はアホォかぁ! 今や平宗盛(たいらむねもり/平氏)は、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の後継者だぞぉ! それこそ馬を見せに行くのではなく、名馬の木の下(このした)を献上しなさい。』
源仲綱…『ええっ〜!? 名馬の木の下(このした)を手放すのぉ〜? クッソォ〜』
こうして源仲綱(みなもとなかつな/朝廷→源氏)が可愛がっていた名馬の木の下(このした)は、平氏の御曹司である平宗盛(たいらむねもり/平氏)に献上されたのである。
そして平宗盛(たいらむねもり/平氏)は、名馬の木の下(このした)の名前を仲綱(なかつな)に変えて、馬のお尻に焼印(やきいん)まで入れた。
そこから平宗盛(たいらむねもり/平氏)は名馬の仲綱(なかつな)を競走馬に鍛え上げて、京都は伏見の淀(よど)にある京都競馬場で参戦して疾走(しっそう)させる事になる。
京都ダービー カッパァン(ゲートが開く音)
パカッパカッパカッパカッ パカッパカッパカッパカッ
秋の菊花賞に出走した名馬の仲綱(なかつな)、スタートは好調!
競馬アナウンサーの杉木清(すぎききよし/実況師)による軽快な解説により、観覧席も盛り上がる。
競馬アナウンサーの杉木清…『早いぞっ仲綱(なかつな)、早いぞっ仲綱(なかつな)、天皇家所縁(ゆかり)の菊の御紋、その菊の季節に平家の名馬が躍(おど)り出る!』
名馬の仲綱(なかつな)は一着でゴールイン!
競馬アナウンサーの杉木清…『やったぞぉ仲綱(なかつな)、やったぞぉ仲綱(なかつな)、今や平氏政権の時代、菊花賞で馬でも制覇! 平家は菊花賞で馬でも制覇!』
偶々(たまたま)にAMラジオを聴いていた元馬主の源仲綱(みなもとなかつな/朝廷→源氏)と父親の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)。
源頼政…『おい、何だ、菊花賞で優勝した名馬の仲綱(なかつな)とは? お前の名前ではないかぁ。』
源仲綱…『そうだよ、親父が名馬の木の下(このした)を平宗盛(たいらむねもり/平氏)に献上しろと言ったから、こんな状況になったんだ!』
源頼政…『うっぐぐぅ〜〜 まさかあの馬が競馬の名馬になり、賞金稼ぎするとは夢にも思わなかったわぁ! わしぃは源氏の“打出の小槌”(うちでのこずち)をみすみす平氏にくれてやったのかぁ!』
急に怒りが込み上げてきた源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)である。
源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)とは、1156年に起こった「保元の乱」(ほうげんのらん)で同じ源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)や平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)と共に第77代天皇の後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)の天皇軍に就いて勝利し、1160年に起こった「平治の乱」(へいじのらん)で同じ源氏の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)を最後で裏切り平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)に味方して勝利し、1177年に起こった「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)で延暦寺(えんりゃくじ)の仏教軍に御容赦を願い命拾いをした源氏でありながら平氏に味方した人物である。
ただ此処(ここ)で、八幡太郎(はちまんたろう)こと源義家(みなもとよしいえ/朝廷)を筆頭に武家の名門家でもある清和源氏の血が漲(みなぎ)る源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が採(と)った行動とは!?
PAT BOONE /♪ AIN'T THAT A SHAME
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:18:28
◆◇◆其の六十九:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
数日後、源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)は、平安京の近くに居住する第77代天皇の後白河天皇(ごしらかわてんのう/朝廷→天皇)の息子の以仁王(もちひとおう/朝廷)の屋敷を訪ねていた。
源頼政…『今や平氏の横暴には目に余る。 此処(ここ)で皇子が皇太子と同列の令旨(りょうじ)を発布すれば、全国の源氏が立ち上がり平氏を倒してみせます。』
以仁王…『う〜〜ん、でもなぁ〜 「鹿ヶ谷の陰謀」(ししがたにのいんぼう)の件もあるしなぁ〜 “平氏討伐”は無理ちゃうかぁなぁ〜』
源頼政…『何を仰(おっしゃ)います! 御父上の後白河法皇(ごしらかわほうおう/朝廷→天皇)も伏見の鳥羽離宮に幽閉されているのですよぉ! 皇子がそんな悠長(ゆうちょう)な考えでは困ります。 平安京が始まって約400年で最大の危機ですぞぉ!』
そこで皇室専属の陰陽師(おんみょうじ)かつシャーマン(呪術師)が祈祷して出した答えを述べた。
シャーマン(呪術師)…『思った時が吉日、今が行動する時でごじゃるぞぉ!』
以仁王…『よっしゃ、やるかぁ!!』
早速、以仁王(もちひとおう/朝廷)は全国の武将や僧兵に“平氏討伐”の令旨(りょうじ)を発布した。
この“平氏討伐”の令旨(りょうじ)を耳にした平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、貿易港として整備し巨万の富を築いていた摂津国(兵庫県)の福原(ふくはら)から、急いで京都の平安京に平氏軍を引き連れて進軍した。
京都に着いた平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が率いる平氏軍は、平氏の拠点でもある六波羅(ろくはら)に陣営を構えた。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)の養子に入っていた源兼綱(みなもとかねつな/朝廷→源氏)に伝令(でんれい)を出して、以仁王(もちひとおう/朝廷)を拘束して六波羅(ろくはら)に連行する様に命じる。
一方、以仁王(もちひとおう/朝廷)と源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)は皇族源氏軍を結成して、岡崎にある白河院(しらかわいん)に陣営を構えた。
そこに源兼綱(みなもとかねつな/朝廷→源氏)が来訪し、義父の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)と以仁王(もちひとおう/朝廷)に、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が率いる平氏軍の多勢が六波羅(ろくはら)に布陣し、合戦の準備に取り掛かっている事を密告する。
源頼政…『うっぐぐぅ〜〜 平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)めぇ〜 もうそこまで来ておるのかぁ〜 取り敢えず白河院(しらかわいん)は危険ですので皇子は近江国(滋賀県)の三井寺(みいでら)に避難して下さい。』
以仁王…『うむっむっ〜 仕方ないあるまい。』
こうして平氏軍に見つからない様に以仁王(もちひとおう/朝廷)は女装して白河院(しらかわいん)を抜け出して、比叡山を越えて園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)に避難した。
この皇子避難作戦は、日本で2番目の“ミスターレディ”と認定されている。
後から源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が率いる皇族源氏軍も、比叡山を越えて近江国(滋賀県)の園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)に移動して陣営を構える。
この園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)は、飛鳥時代の「大化の改新」の中大兄皇子(なかのおおえのみこ)こと第38代天皇の天智天皇(てんぢてんのう)、「壬申の乱」の大海人皇子(おおあまのみこ)こと第40代天皇の天武天皇(てんむてんのう)、その妻の鸕野讃良(うののさらら)こと第41代天皇の持統天皇(じとうてんのう/女皇)に所縁(ゆかり)のあるお寺でもある。
第72代天皇の白河天皇(しらかわてんのう/朝廷)が子宝祈願で訪れた時に、住職の頼豪(らいごう/僧侶)の対して延暦寺(えんりゃくじ)が戒壇(かいだん)の設置に反対した事で失礼を働き、断食修行で命を落とし怨霊の鉄鼠(てっそ/妖怪)に化けた事でも有名であった。
その頃から同じ天台宗(てんだいしゅう)でも、近江国(滋賀県)の比叡山に建つの延暦寺(えんりゃくじ)と園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)は因縁の間柄(あいだがら)となっている。
その園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)の僧兵も参戦する事になり、皇族源氏仏教軍に増強された。
しかも、“南都”(なんと)の大和国(奈良県)にある興福寺(こうふくじ)の僧兵も協力する内諾を取り付けた。
“南都”(なんと)とは、大和国(奈良県)にある法相宗(ほっそうしゅう)の興福寺(こうふくじ)の事で、そこに配備された僧兵を奈良法師(ならほうし)と呼んだ。
当然に園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)と“南都”(なんと)の興福寺(こうふくじ)とは犬猿の仲である“北嶺”(ほくれい)の延暦寺(えんりゃくじ)は参戦しない。
“北嶺”(ほくれい)とは、近江国(滋賀県)にある天台宗(てんだいしゅう)の延暦寺(えんりゃくじ)の事で、そこに配備された僧侶を山法師(やまほうし)と呼んだ。
そして皇族源氏仏教軍の大佐クラスが軍略会議を開催して作戦を策定した。
内容は“六波羅夜襲作戦”(ろくはらやしゅうさくせん)である。
深夜に皇族源氏仏教軍の先制部隊を比叡山を越えて白河院(しらかわいん)に布陣して、周辺の民家に火を放ち地域一帯を延焼させて、六波羅(ろくはら)に陣営を構える平氏軍を誘き寄せる。
次ぎに、平氏軍が白河院(しらかわいん)に進軍している間に、防衛の手薄となった六波羅(ろくはら)の本陣を、皇族源氏仏教軍の主力部隊が総攻撃を仕掛けて平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)を討ち取る計画であった。
ところが、この“六波羅夜襲作戦”(ろくはらやしゅうさくせん)に待ったを掛ける者が現れた。
それは軍略会議に出席していた阿闍梨(あじゃり)の高位な僧侶で真海(しんかい/僧侶)だった。
真海…『そんな子供騙しみたいな戦術で、あの強靭な武力を持つ平氏軍は倒せませんぞぉ! もっと緻密(ちみつ)に戦略を練る必要がある。』
こうして皇族源氏仏教軍の軍略会議は長々と続き、東山に朝日が上り夜明けを迎えるのであった。
コケコッコ〜
一番鶏が鳴いたところで真海(しんかい/僧侶)が立ち上がる。
真海…『ちょっと厠(かわや)で糞(クソ)してくる。』
そう言って会議室を出て行ったが、二度と戻ってこなかった。
実は真海(しんかい/僧侶)は、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)が送り込んだ間者(かんじゃ/スパイ)だったのである。
そのまま園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)を後にした真海(しんかい/僧侶)は、皇族源氏仏教軍の追手(おって)を警戒して山科を経由して六波羅(ろくはら)の平氏軍の陣営に駆け込んで、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)に諜報報告をした。
真海…『皇族源氏仏教軍は“六波羅夜襲作戦”(ろくはらやしゅうさくせん)を企てていますが、一応は実行を引き延ばしさせています。』
平清盛…『うむっ、御苦労であった。』
THE OVATIONS /♪ IT'S WONDERFUL TO BE IN LOVE
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:19:31
◆◇◆其の七十:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
此処(ここ)から平氏軍を率いる平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の本領発揮と出る。
平氏軍の特殊部隊のHAT(ヘイシ・アサルト・チーム)も出動準備を完了している。
厠(かわや)に糞(クソ)しに行って戻って来ない真海(しんかい/僧侶)の裏切りに気付いた以仁王(もちひとおう/朝廷)と源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)は、近江国(滋賀県)の園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)は、京都の六波羅(ろくはら)と距離が近い為に危険と感じて、大和国(奈良県)の興福寺(こうふくじ)に移動する事にした。
その時に園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)の僧兵の、猛将で有名な矢切但馬(やぎりたじま)こと五智院但馬(ごちいんたじま/僧兵)、弓の名手の浄妙明秀(いじょうみょうめいしゅう)こと筒井浄妙(つついじょうみょう/僧兵)、その弟子の一来法師(いちらいほうし/僧兵)なども同行した。
皇族源氏仏教軍は、近江国(滋賀県)の園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)から南下して伏見の稲荷山を経由し大和国(奈良県)の興福寺(こうふくじ)に向かう途中、宇治川を渡った藤原氏所縁(ゆかり)の平等院(びょうどういん)に立ち寄り休息した。
その情報を掴(つか)んだ平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は、平氏軍を宇治の平等院(びょうどういん)に侵攻させた。
宇治川を挟んで北方に平氏軍は布陣し進撃の構えを見せ、南方の平等院(びょうどういん)に皇族源氏仏教軍が布陣し防御の構えで応戦する。
平氏軍は宇治川に架かる木造の宇治橋を渡り南方を目指すも、橋の途中から敷板が外されており、大群で押し寄せる平氏軍の兵士は群集雪崩(ぐんしゅうなだれ)の現象で、次々と兵士が川に落ちていき流されていった。
その数はざっと200人あまり。
更に橋の中央で待機していた皇族源氏仏教軍の僧兵の、矢切但馬(やぎりたじま)こと五智院但馬(ごちいんたじま/僧兵)は飛んで来る矢を次々と打ち落とし、橋を渡ってきた平氏軍を斬り付ける。
弓の名手の浄妙明秀(いじょうみょうめいしゅう)こと筒井浄妙(つついじょうみょう/僧兵)と、その弟子の一来法師(いちらいほうし/僧兵)も矢を射って平氏軍の兵士を倒し、平氏軍の陣地まで乗り込み太刀(たち)や薙刀(なぎなた)で兵士を斬り付けていった。
宇治川により苦戦する平氏軍は一時撤退を余儀なくされる。
そして、体制を立て直した平氏軍は、宇治川に大きくて強い馬を何頭も横に並べて上流の川の勢いを弱める馬筏(うまいかだ)だった。
此(こ)れにより宇治川の南方に上陸した平氏軍は、皇族源氏仏教軍が布陣する平等院(びょうどういん)に進撃を開始する。
戦況不利と見た源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)は、皇子の以仁王(もちひとおう/朝廷)を先に逃亡させて大和国(奈良県)の興福寺(こうふくじ)に行く様に伝える。
その間、源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)が率いる平等院(びょうどういん)に残った皇族源氏仏教軍が応戦した。
源頼政…『もはや、これまでか?』
そう言い残した源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)は、家臣に介錯(かいしゃく)を頼み、斬首した首級(しゅきゅう)は平氏軍の手に渡らない様に宇治川に沈める様に指示した。
最後の最後で、八幡太郎(はちまんたろう)こと源義家(みなもとよしいえ/朝廷)を筆頭に武家の名門家でもある清和源氏の血が漲(みなぎ)る74歳だった老兵の源頼政(みなもとよりまさ/朝廷→源氏→平氏→源氏)の取った行動は、後世に流石(さすが)は源氏との賞賛(しょうさん)を浴びる。
ただ、先に逃した以仁王(もちひとおう/朝廷)も途中の山城国(京都府)の相楽郡(そうらくぐん/南山城)で平氏軍に追い付かれて、兵士の弓矢を射った矢に当たり絶命した。
迎えに来た“南都”(なんと)の興福寺(こうふくじ)の奈良法師(ならほうし)が、あと少しの処(ところ)まで来ていた中での悲劇である。
これを1180年に起こった「以仁王の令旨」(もちひとおうのりょうじ)と呼ぶ。
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)は戦後処理として、敵対した近江国(滋賀県)の園城寺(おんじょうじ)こと三井寺(みいでら)を焼き討ちにして焼失させた。
大和国(奈良県)の興福寺(こうふくじ)は、藤原氏も怯(おび)えた武装集団の僧兵である奈良法師(ならほうし)に警戒して、京都の平安京から摂津国(兵庫県)の福原(ふくはら)へ都(みやこ)を遷都(せんと)し福原京(ふくはらきょう)を創建し始め距離を置いた。
此(こ)れにより平安京は都(みやこ)としての機能を失い荒廃していく。
後日談では、以仁王(もちひとおう/朝廷)が御触(おふれ)を出した“平氏討伐”の令旨(りょうじ)について、平安京の朝廷は把握しておらず、後々に正式文書では無いと平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)に説明している。
なんせ第81代天皇の安徳天皇(あんとくてんのう/朝廷)は平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の孫で、就任したばかりの2歳であり、朝廷で何が起こっても不思議では、無い!
EDDIE JEFFERSON /♪ WHEN YOU LOOK IN THE MIRROR
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:20:31
◆◇◆其の七十一:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
平清盛(たいらきよもり/朝廷→天皇→平氏)に反旗を翻(ひるがえ)し1160年に起こった「平治の乱」(へいじのらん)で敗北した源氏の棟梁でもある源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)は、尾張国(愛知県)の知多半島の野間(のま)まで逃亡するも、ここで味方に裏切られ入浴中に討死する。
一方、その頃、青年だった源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)も「平治の乱」(へいじのらん)に参戦しており、敗北した事を知ると京都の平安京から近江国(滋賀県)の米原を経由して美濃国(岐阜県)の関ヶ原まで逃亡する。
そこから生まれ故郷の尾張国(愛知県)の熱田神宮に祀られる小碓命(オウスノミコト)こと倭建御子(ヤマトタケルノミコ)に匿(かくま)ってもらう予定が、美濃国(岐阜県)と尾張国(愛知県)の国境に流れる木曽川辺りで迷子になる。
源頼朝…『ヤベェ〜 何処(どこ)なのか分からなくなったぁ!?』
しかも、逃亡中に美濃国(岐阜県)の金津園(かなづえん/遊郭)で豪遊をしてしまい、お金はすっからかん。
グゥ〜グゥ〜 グゥ〜グゥ〜
源頼朝…『お腹空いたなぁ〜 故郷(ふるさと)の熱田神宮に行ったら“ひつまぶし”をたらふく食べよぉ〜』
取り敢(あ)えずヒッチハイクして飛脚(ひきゃく)の大型トラックに乗せてもらった。
しかし、その大型トラックは駿河国(静岡県)から美味しいミカンを運んで近江国(滋賀県)に行く途中だった。
近江国(滋賀県)に入り瀬田の唐橋(せたのからはし/大津)を渡り石山寺の前で降ろしてもらった。
源頼朝…『おじちゃん、ありがとぉ〜』
トラックの運転手…『おうっ、坊やも元気で達者で暮らせよぉ!』
大型トラックから降りる間際に源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は、父親の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)から『最後の最後で困った時に助けてくれた恩人に、この封筒を渡しなさい。』と言われ受け取っていた大切な薄い茶色の封筒を、御礼にトラックの運転手に手渡した。
その薄い茶色の封筒の中身を見たトラックの運転手は、泥(どろ)の付いた1万円札が3枚入っている事に気付いた。
トラックの運転手…『俺、受け取れねぇ〜 これは受け取れねぇ〜』
源頼朝…『えっ!? でも、亡くなった父上から、親切にしてくれた恩人に渡しなさいと言われているので、どうぞ受け取って下さい。』
トラックの運転手…『坊や、この泥(どろ)の付いた1万円札の3枚を見ろぉ! どんな気持ちで亡くなった父親がお前の事を案じていたか。 だから、俺は受け取れねぇ〜 坊やよぉ、この薄い茶色の封筒を一生涯、御守りとして手放すんじゃねぇぞぉ!』
そう言ってトラックの運転手は何も受け取らず行ってしまった。
そんな処(ところ)に平氏軍の落武者狩りが現れて、源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は拘束される。
京都の六波羅(ろくはら)に居住する平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の前に、源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は突き出される。
平清盛…『この小僧が源氏の棟梁となる息子かぁ! 父親の源義朝(みなもとよしとも/朝廷→天皇→源氏)に似て男前だのぉ〜』
源頼朝…『むっ!』
源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は、青年ながらに平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)を睨(にら)み付ける。
平清盛…『父親に似ていると言う事は、小僧が大きく成れば平氏政権に牙(きば)を剥(む)くかも知れんのぉ〜 おいっ、この小僧を五条河原で斬首して晒し首(さらしくび)にしとけっ!』
平時忠…『はっ! 仰(おお)せの通りに致します。 小僧、こっちに来いっ!』
平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の義弟の平時忠(たいらときただ/朝廷)に命じて、青年の源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は死罪となった。
池禅尼…『ちょっと待って下さぁ〜〜い! その子を死罪にしないでぇ〜』
此処(ここ)で平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の継母の池禅尼(いけのぜんに/藤原→平氏)から“ちょっと待ったコール”が入った。
池禅尼…『こんな可愛い子を斬首するなぁんてぇ、絶対にダメですぅ! この子を見ていると、以前に生まれ短い生涯を終えた息子にそっくりで、我が息子の様に思えてくるのぉ!』
平清盛…『う〜〜ん でも義母さん、この小僧の目を視(み)れば、必ずや平家一門に反乱を起こす予感がするんですよね。』
池禅尼…『分からずやぁ! あんたぁみたいな薄情な息子を産んだ覚えは無い! ならぁ、この私を先に斬首しなさいっ! そしてこの子と一緒に並べて五条河原で晒し首(さらしくび)にするといいわぁ! 母親が子供の命を守るのは当然の母性本能よぉ!』
平清盛…『義母さんから産まれてはいないけどね。 でもぉ困ったなぁ〜 まあ、いいかぁ。 その代わり伊豆国(静岡県)に流刑として、出家して仏門に入り僧侶と成って、二度と武士に成らぬ事が条件であるぞぉ!』
池禅尼…『よかったわねぇ〜、ボク。』
源頼朝…『おばちゃん、ありがとぉ〜』
源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は御礼に、池禅尼(いけのぜんに/藤原→平氏)に宛(あ)てて歌を詠んだ。
源頼朝…『♪チョット マッテ クダサァ〜イ 桜は春に〜 心は弾(はず)む〜 桜も散って〜 今は哀しい〜 チョット マッテ クダサァ〜イ 優しい〜 母君と別れるのは辛い〜』(♪チョットマッテクダサイ)
池禅尼…『ウッウッウッ〜 なんて優しい歌なの。 こんな子が平氏に対して謀反(むほん)を起こすなんて絶対にありえません!』
平清盛…『ウッウッウッ〜 ワァ〜〜ン ワァンワァン ワァ〜〜ン なんて良い歌なんだぁ〜 感動したっ!』
池禅尼(いけのぜんに/藤原→平氏)とは、平清盛(たいらきよもり/朝廷→平氏)の父親の平忠盛(たいらただもり/朝廷)の正妻で、古くから源氏と蜜月な関係にある藤原氏北家(ほっけ)の系統である。
ARCHIE BELL & THE DRELLS /♪A SOLDIER'S PRAYER
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友 URL
2025/01/08 (Wed) 16:21:27
◆◇◆其の七十二:京都の平安京に棲(す)み着き漂(ただよ)うエイリアン◆◇
1160年に、伊豆国(静岡県)の蛭ヶ小島(ひるがこじま/韮山)に流刑となった源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)。
この地では、出家して僧侶となり戒律の厳しい仏教への道へと進み、仏門では坊主頭でお経を唱える日々が続いた。
ポクポク ポクポク
源頼朝…『南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、まんまんちゃん、まんまんちゃん、あ〜〜ん!』
チィ〜〜ン
源頼朝…『よしぃ! 念仏はここまでっ。』
和尚さん…『うむぅ、頼朝(よりとも)も立派な僧侶に成長したのぉ〜』
源頼朝…『いやっ、和尚さん、慢心(まんしん)はいけませぬ! 続いて身体を鍛える為に伊豆半島をランニングで一周してきます。』
そう言って源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は、赤色のアディダスのスポーツウェアに着替えて、スニーカーもアディダスの黄色いランニングシューズを履いお寺を出ていった。
和尚さん…『関心、関心、後々はあの謹厳実直(きんげんじっちょく)な頼朝(よりとも)に、このお寺を継がせよう。 これで一安心じゃ。』
ランニングをする源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は、蛭ヶ小島(ひるがこじま/韮山)から熱海の下部辺りにある伊東まで走り抜けると、そこに建つ立派な御殿に忍び込んだ。
温泉付きの1万5000㎡(4537坪)もある此処(ここ)の屋敷は、伊豆国(静岡県)の伊東の武将で平氏に仕える伊東祐親(いとうすけちか/平氏)の立派な御殿だった。
そこの娘の八重姫(やえひめ/平氏→源氏)と恋仲になり、源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)は時折(ときおり)この屋敷に訪れては情事(じょうじ)を楽しんでいた。
しかも、家主で父親の伊東祐親(いとうすけちか/平氏)は、京都の平安京に出向しており不在だった。
源頼朝…『いやぁ〜 蛭ヶ小島(ひるがこじま/韮山)から伊東まで走って来ると、汗がビッショリだっ! 一緒に温泉に入ろうぜぇ!』
八重姫…『はい、頼朝(よりとも)様、お背中を流させて頂きます。』
そう言って愛する若い2人は、伊東祐親(いとうすけちか/平氏)がご自慢の温泉に浸かった。
ザブ〜〜ン
源頼朝…『いやぁ〜 伊豆の温泉は最高だなぁ〜 京都の平安京には天然温泉なんてないからなぁ〜 お前ももっと此方(こちら)に寄らぬか。』
八重姫…『はい、でも頼朝(よりとも)様に見つめられると恥ずかしくて、身体が変に火照(ほて)ってきますわぁ。』
源頼朝…『ヘェヘェヘェ〜 では、もっと火照(ほて)る様に、これでもどうだぁ!』
グイグイ グイグイ
八重姫…『あれぇ〜 お戯(たわむれ)をぉ〜』
こうして乙女だった八重姫(やえひめ/平氏→源氏)は、源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)の色に染まっていった。
そんなある日・・・
八重姫…『頼朝(よりとも)様、実は赤ちゃんができたみたいで。』
源頼朝…『おおっ〜 わしぃに子供かぁ! でかしたぞぉ!』
そうして父親の伊東祐親(いとうすけちか/平氏)が不在の中、八重姫(やえひめ/平氏→源氏)は源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)の息子を出産して、名前を千鶴御前(せんつるごぜん/源氏)と付けた。
ところが、父親の伊東祐親(いとうすけちか/平氏)が京都の平安京での任期を終えて、伊豆国(静岡県)の伊東へ戻ってきたらビックリ!!
何と未婚の娘が赤子を抱いているではないかぁ!
伊東祐親…『おっ、お前!? 抱いている赤子は誰なんだぁ?! 保育士になって預かっているのか?』
八重姫…『ううっん、この子は頼朝(よりとも)様との赤ちゃんで、名前は千鶴御前(せんつるごぜん/源氏)と申します。』
伊東祐親…『頼朝(よりとも)様? えっ!? あの源氏の棟梁の家系でもある源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)の事か?』
八重姫…『はい、お父様、その通りで御座います。』
伊東祐親…『お前ぇ〜 ウチは平氏に仕える身分だぞぉ! しかも源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)の息子なら嫡男(ちゃくなん)ではないかぁ! 平氏に知られたらただじゃ済まないぞぉ! こうしちゃおれん、その赤子を渡すのだぁ!』
八重姫…『嫌ぁ〜 離してぇ〜 私の赤ちゃんを返してぇ〜〜』
こうして父親の伊東祐親(いとうすけちか/平氏)は、源頼朝(みなもとよりとも/鎌倉)と娘の八重姫(やえひめ/平氏→源氏)の息子の千鶴御前(せんつるごぜん/源氏)を取り上げて、伊豆半島の中央部にある河津七滝(かわづななだる)に沈めたのであった。
BEN E.KING /♪ SPANISH HARLEM
◆ラジオの友◆
Re: 今日の1枚、お薦めレコード/20250108 - ラジオの友
2025/02/10 (Mon) 22:06:15
テスト